月刊ココア共和国 (電子本&紙の本) について
☆11月号☆ (2021.10.28)
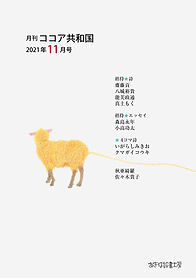
目次
●今月の一行
現代詩お嬢様
●招待詩
齋藤 貢「こころ」
八城裕貴「あるいていると」
能美政通「幽谷」
真土もく「人たち」
●招待エッセイ
森島永年「戯曲」
小高功太「私は常に詩ょう気(正気)ではない」
●11月号投稿詩人のみなさんへ
秋吉久美子
いがらしみきお
●投稿詩傑作集Ⅰ
京のふじ「あぐらかき人形」
古谷祥多「あるの反対はない」
南雲薙「不思議」
青木桃子
「オレンジ色のケーキ、黄色のばあちゃん」
かとうみき「ビールクズのつぶやき」
小峰浩義「挿し木で増える」
和本果子「タイムカプセル」
向坂くじら「死ぬ前の話」
小原琢万「ヒメアリの葬列」
道下 宥「宛先不明」
大野美波「いつも」
腹巻さしみ「ホーム」
豊田隼人「逆張りの詩」
現代詩お嬢様「たとえば十月について」
野崎小指「タンポポを潰さないで」
●4コマ詩
いがらしみきお「雲にいる」
秋亜綺羅「詩論」
佐々木貴子「あなたはどれを倒すか迷う」
クマガイコウキ「私を呼ぶ人について」
●投稿詩傑作集Ⅱ
平松秀章「絵画の迷子」
高平 九「昨日と同じように」
木崎善夫「契約カメラマン・森山太造の失踪」
市丸よん「ヘラクレイトス」
ことぶき「サンタクロース」
塚本 愛「数えてばかり」
波崎 佑「卵のような黄身の目玉」
景「ダンス」
げん「彼女はわたし 渋谷バス停で」
山田迷路「あなたはすべてを誤読する」
山羊アキミチ「ステップ・ノワール」
井上菜ズナ「遊泳」
ゐしもりみづゑ「交差する点景」
nma流雲「心」
●エッセイ
佐々木貴子「あの時」
秋亜綺羅「裏の裏には裏がある」
●投稿詩傑作集Ⅲ
岩佐 聡「井戸の訪い」
滝本政博「晩夏」
木村キリコ「私のため」
菅沼きゅうり「籠の中の鳥」
木葉 揺「メッセージ」
茉莉亜・ショートパス「クロバネキノコバエ」
でおひでお「最後の灯り」
佐倉 潮「数式たち」
狩野慶太「コインランドリー」
遠藤健人「外注」
吉岡幸一「愚か者」
あち「自律神経出張中」
中原賢治「清掃から焼却へ」
大西久代「薬売り」
竹井紫乙「金曜日」
●詩
佐々木貴子「その時」
秋亜綺羅「詩」
あきは詩書工房では、2020年4月1日に月刊詩誌「ココア共和国」を創刊号として、フィックス版と紙の本で刊行しました。ゲストや編集同人による詩、エッセイなどを中心に、詩の理論と方法論を追究しています。
また全国から詩の投稿を募集し、素敵な投稿作品をたくさん掲載していきます。
「ココア共和国」への投稿詩は同時に、2021年12月31日に締め切られる「第2回いがらしみきお賞」「第2回秋吉久美子賞」へ応募されたものとみなされます。20歳未満の方はそれらに加え「第7回YS賞」の3つの賞に応募したことになります。
「月刊ココア共和国」 電子本の発売は各ネット書店より。275円(税込)。
紙の本はココア・ショップまたはAmazonで販売しています。770円(税込)。
<編集前記>
日本では新型コロナもやっと終息が近いのかなと思えるようになりました。海外との交流が、これからの課題になるでしょうね。2年間、コロナのおかげで、文化イベントは「不要不急」とされてしまいました。だけど文化だってスポーツだって、政治と違って国境のない未来への可能性を秘めているわけです。失われた2年を無駄にしないように頑張ってきたつもりのココア共和国ですが、今後は新型ココアとして、たくさん仕掛けていきますよ。変異もありますよ。
ではさっそく、11月号の紹介です。
今月の詩のゲストは、齋藤貢。秋吉久美子賞の選考委員で毎月の投稿詩に「絶賛」を選んでもらっています。日本現代詩人会の現代詩人賞をとった、福島県の偉い詩人なのです。原発事故以後を深い抒情で鋭く突いているところを味わってください。
3賞受賞者の作品も八城裕貴、能美政通、真土もくと今月も3名揃っています。3名とも完成された詩人をめざすのでなく「詩の実験人」としての活躍を期待しています。寺山修司が主宰していた「天井棧敷」が「劇団天井棧敷」ではなく「演劇実験室天井棧敷」と称されていたように。
招待エッセイは森島永年と、ココア代表には小高功太に。詩や文学や言葉に関する考えを自由に書いてもらっています。森島は、わたしが大学生時代に静岡県清水市の喫茶店で詩の朗読で呼ばれた時に、アコギを弾いていた高校生でした。その後森島は劇団を作って劇作家になっていて、10年ほど前にSNSかなんかで再会? となりました。小高はご存知の方も多いと思いますが、既成の作家やその作品をパロディにしたり洒落として詩に利用します。ユーモアがいっぱいで楽しめます。そんな小高のエッセイもまた、笑えるところがすごいですね。
4コマ詩はいがらしみきお、クマガイコウキ、秋亜綺羅、佐々木貴子。
秋吉久美子といがらしみきおからは、投稿詩への短評と「いいね」を。齋藤貢からも「絶賛」をもらっています。電子本の「佳作」にもたくさんの「絶賛」や「いいね」があります。チェックしてみてください。
では、投稿詩をいくつか。
豊田隼人の「逆張りの詩」は、タイトルどおりの詩。実はわたし自身にとっての詩もまったくこの通りなのだけど、みなさんはいかがでしょう?
現代詩お嬢様「たとえば十月について」はうまいなぁ。第1連だけで虜になってしまいました。緊迫したナンセンスが最後まで続くのだから、ちょっとヤバい!
野崎小指の「タンポポを潰さないで」もいい。タンポポが本文に出てこないのに、わかるような気がしてしまう。生きることは殺すこと。最初の行「黒が好き、血が好き、」と来て重くなりそうなところを「雨が好き、」と逃げているのも才能だね。
滝本政博「晩夏」は「夢の中で母を殺したのに/朝になったらまだ生きている」と始まります。当たり前と言えばそうなのですが、その後、夢と現実の境界が曖昧になっていきます。最終行は、現実なのだろうか? 面白い。
菅沼きゅうりの「籠の中の鳥」は「皮膚病のセキセイインコが死んで」と始まります。中年の女性が夫婦のことを書いている詩のようだけれど、菅沼は2002年生まれだよね。最後に、籠の中の鳥は自分だったことに気づくのでした。
ほかにも劇的な詩があふれていますよ。掲載にならなかった詩たちも、今後が楽しみなものばかり。
ココア共和国には、読者の心を虜にしてしまうたくさんの詩たちが待っています。すさまじい体験になることでしょう。
(秋亜綺羅)
<編集後記>
皆さま、いかがお過ごしですか。ほんの少し前まで蝉の鳴き声や、昨年と今年のコオロギの比較のための音源とりに夢中になっていたのですが、あっという間に冬支度となりました。え? ハロウィン? クリスマス? 年賀状? え? ココア共和国? 現時点でも第2回秋吉久美子賞、第2回いがらしみきお賞、第7回YS賞のことを気にしながら、心は2021年から2022年へと行き来しています。
11月号は9月末日で締め切った投稿作品を選考し、掲載しました。毎号、指摘したところで特に何か意味があるわけではないですが、やはり申し合わせたのかなと思うほど、月ごとに投稿作品の中に多く用いられる言葉があるようです。今回は金曜日、8月32日、天使、神、海、人魚、木琴、花などでした。たぶん、様々な楽曲やココアの前号にインスパイアされた作品も少なからず投稿されているのでしょう。また今号に関しては特に著者に確認してみなければ分からない句読点のほか、誤字脱字も多く見られ、これまで以上に問い合わせと確認を経て出来上がったココアになりました。詩人なら言葉の裏も表も、隅々にこだわりを持って当然です。今更ですが、投稿者の方々と一緒にココアを作っているのだと感じました。本当にありがたいことです。
今号は傑作集に44篇、佳作集(電子本にのみ所収)には107篇を掲載しました。11月号は151人の投稿詩を味わっていただけます。さらに今回は新たに秋吉久美子「ちょっといいね」をいただきました。別枠で、ちょっと、です。読者の皆さま、ニュアンスの違いを楽しんでくださいね。
それでは投稿詩を少しだけご紹介しましょう。青木桃子「オレンジ色のケーキ、黄色のばあちゃん」、全く説明的ではないのに身体性を十分に想起させ、喪失の情景を色彩豊かに描いています。各連で少しずつ時間の速度を変えて、地名を詩行にスッと入れるところも巧みだと感じました。小峰浩義「挿し木で増える」の世界観、増殖するイメージにとても魅力を感じました。わたしたちの言葉も挿し木で増えるタイプでしょうか。京のふじ「あぐらかき人形」、とにかくこの設定に脱帽です。1行目から早速、跳躍しています。人形と人間のあいだに「あぐらをかく」ことの両義性を読み込むことができるなんて、もう人間業とは思えません。和本果子「タイムカプセル」、リアルと非リアルが交叉しつつ、リアルが凌駕される一瞬を堪能できます。ぜひこの作品の最終連で体験してください。古谷祥多「あるの反対はない」は、説明的であることを厭わずに、むしろ突き進むところに好感が持てました。やや弱気な側面が「気がする」「かもね」に散見されたのですが、そんなことはない! と、タイトルに叱られました。かとうみき「ビールクズのつぶやき」、詩型とは逆行する方法で、生の感触を際立てることに成功しています。小原琢万「ヒメアリの葬列」、この感覚が詩に描かれたことにまず驚きました。最初は秘密の昆虫図鑑を開き、覗き見している心境でしたが、最終連で鳥肌が立ちました。道下宥「宛先不明」の抒情はよく沁みます。内容もさることながら読点がこうして宛先不明のための余韻を醸し、万年筆から滴るものになったことに言葉の可能性を強く感じました。岩﨑風湖「いいとこ いいとこ」、1連目に誘われウキウキついて行くと詩は一見、一枚仕立ての地図にも感じるのですが、実際は多義的な読みの切り口が千鳥がけの飛石状に配置され、それによって立体感が強調された作品だと分かりました。伊渓路加「撃たれた声」は音を読ませる詩でした。本当は4連目の「野良猫さん/ひとり静かに死なないで!」に全部、凝縮されているのかもしれません。もし、そうであったとしたら2連目に特に直喩を用いなくても、空に無数の穴が穿たれるのではないでしょうか。金平糖流星群「何も始まっていなかった」、興味深く読みました。終始、この「終/始」で貫くならば、詩行を右から左に読む以外にも、最終行から1行目に向かって読むことも可能だったのではないかと思います。実際、そのようにならないのは4連目の重点化があるからでしょう。内田安厘「花の下で死にたい」を読み、生きるための儀式という視点を見出した気がしました。思うに、桜の精はどうしても満開の桜を恋しがるようにできているのです。シーレ布施「ファンレター」、眩しくてたまりません。言葉が今にも弾けそう。どうぞ皆さま、何度読んでも鮮度が落ちない理由を探してくださいね。魚眼石「宇宙飛行士の僕らは孤独の世界を飛び続ける」、魅力的なタイトルに作品自体が凝縮されています。またロケット発射後に浮遊し続ける苦しさや「手をのばす」身体としてのリアルなありようが詩からとにかく溢れています。これが、とてもとても切ない。「孤独に耐えうる身体をつくって」飛び立ったはずなのに心は動く。横山大輝「あ。」も優れて冒険的な詩です。3行12回ずつの「痛い」。なぜか3年分の「痛い」のようにも読めました。「朝焼けの澄み切った、希望を見せる空は/私を失明させた」という魅力的な詩行。一度でもいいから、この詩の朗読が聴きたいです。この他、木崎善夫「契約カメラマン・森山太造の失踪」、波崎佑「卵のような黄身の目玉」、ゐしもりみづゑ「交差する点景」、竹井紫乙「金曜日」、南雲薙「不思議」、市丸よん「ヘラクレイトス」、塚本愛「数えてばかり」、平松秀章「絵画の迷子」、ことぶき「サンタクロース」、山羊アキミチ「ステップ・ノワール」、中田野絵美「人魚の家」、岡本彩花「きみは死ぬから美しい」、おののもと「父親と息子」、うみの奈波「心音」、すみれ「椿の花は首から落ちる」も繰り返し読みました。ぜひ、おススメしたいです。
毎月の投稿、期待しています。
(佐々木貴子)
▼以下は電子版のみに収録❤
●投稿詩佳作集Ⅰ
中田野絵美「人魚の家」
岩﨑風湖「いいとこ いいとこ」
傘さやか「愛が汚した」
太田尾あい「あむ」
内田安厘「花の下で死にたい」
嘉村詩穂「羽葬」
英田はるか「らっきょうのうた2」
助廣俊作「言葉のあや」
シバフネコ「パンツはワレモノではありません」
裏路地ドクソ「森の王は死んだ」
宇月五月「私はヒトとは違ってさ」
渋谷縷々子「八月三十二日」
雨野小夜美「クロール」
糖花「心臓を食べる」
熊野コエ「哺乳類」
吉田広行「そこから始まるものは」
伊渓路加「撃たれた声」
園 イオ「人魚とデート」
日和リョーナ「おはようをつくる彼」
遠海トンビ「ハッブル、ルメートル、君と僕」
近藤太一「染まる」
横山大輝「あ。」
林 やは「躍りの詩」
のぐちみね「うお座」
篠崎亜猫「君、遠方より」
帛門臣昂「夜毎の事」
喜島茂夫「廃車」
サカイユウダイ「砂漠に壁が」
手塚桃伊「胎児の夢」
白萩アキラ「乾かない感触」
如月幽慶「八月の君のための習作」
ツチヤタカユキ「Blink Traverar」
金森さかな「鈴虫」
露野うた「熱」
髙橋甚太「マーダーボール」
いずみ「今度生まれ変わったら?」
ネオバタ君「黄泉のワタリドリ」
眞木西陽「昔の昨日のこと」
魚眼石
「宇宙飛行士の僕らは孤独の世界を飛び続ける」
●エッセイ
佐々木貴子「どうにもまとまらない♪ ⑧」
●投稿詩佳作集Ⅱ
野宮ゆり「水の糸」
多田隈倫太「消すことへの恐怖」
金平糖流星群「何も始まっていなかった」
しらすこう「シガレットブルース」
エキノコックス「あお」
たなかひろし「ナントカ相対性理論」
竹之内稔「無言の刻」
熊野ミツオ「生きている意味」
石川順一「席替え」
鈴木明日歌「八月三十二日」
星堕位置「作品No.59」
天 茉莉「ヨネあんにゃ」
才木イチロウ「リバース」
みたこ「あしたの食卓」
シーレ布施「ファンレター」
三木ちかこ「雪うさぎ」
田村全子「たまに憂鬱」
真城六月「この世の歌」
すみれ「椿の花は首から落ちる」
清水深愛「DEEPLOVEDOLL」
めい「So S ?」
岡本彩花「きみは死ぬから美しい」
八十一慶「テイッシュペーパー」
おののもと「父親と息子」
うみの奈波「心音」
木山瑠美「オアシスはまだ見えない」
三泉みすい「Cherub Song」
西川真周「乳首予備軍」
西岡俊貴「ある完全」
月島 奏「巣立ち」
化野道夢「ビッグバン」
真殿こあら「あなたを忘れない」
汐咲「救急車のてつお」
吉谷 悟「僕の優しさ」
空蝉「嫌な人間の願い」
森崎 葵「金曜日は余生」
片野翠子「みのほどしらず」
●エッセイ
秋亜綺羅「『ひよこの唄』の題字を書きました」
●投稿詩佳作集Ⅲ
暦「プラトニック恋愛思想」
緑の葉っぱ「ウォシュレットを教えてくれた子」
隅野R「はなばたけじごく」
東京花束「ピンクの人」
半田一緒「金 四萬円」
山口波子「対等な葬送」
あさとよしや
「トイレのタイルのシミ、かくかたりき」
木倉 蓮「白花で満ちた棺はない」
岩崎淳志「陰話」
深田 良「道端一人旅」
原島里枝「半身をさがして」
南川康太郎「悪魔ホスピタル」
十羽ひのこ「コットンキャンディー」
佐之市いつき「駄目人間」
結咲こはる「凍った棘が刺す夜」
あさ「六等星」
西條成美「私の名前は」
五十嵐あかり「創世夜」
北川 聖「青い鳥」
井田みゆう「チョコレート」
斉藤木馬「帰港」
柳沢 進「夜の指令」
背野順「青と赤の学校生活」
川﨑愛弓「箱」
橘こはく「製紙工場」
早川佳希「ちょうちょもぼくらのように」
荒木章太郎「なみうち際で君と会うたしなみ」
鴉鷺「Tui fui, Ego eris.」
双星たかはる「マリトッツォ」
soomilee「95%」
枝瀬 優「五十万円」
<執筆者>
☆秋亜綺羅 (あき・あきら)
詩人。1951年生。宮城県在住。
詩集に『透明海岸から鳥の島まで』(思潮社・2012)、『ひよこの空想力飛行ゲーム』(思潮社・2014)、『十二歳の少年は十七歳になった』 (思潮社・2021)など。エッセイ集に『言葉で世界を裏返せ! 』(土曜美術社出版販売・2017)。丸山豊記念現代詩賞。
☆秋吉久美子 (あきよし・くみこ)
俳優、歌手、詩人。1954年生。
『十六歳の戦争』『赤ちょうちん』『妹』など主演多数。アジア映画祭主演女優賞、日本アカデミー賞優秀女優賞、ブルーリボン賞主演女優賞、モナコ国際映画祭主演女優賞など受賞多数。詩集に『いない いない ばあ』『C・U next tuesday』など。
☆いがらしみきお
漫画家。1955年生。宮城県在住。
『ネ暗トピア』『ぼのぼの』『BUGがでる』『3歳児くん』『かむろば村へ』『I』など多数。
日本漫画家協会賞優秀賞、講談社漫画賞、小学館漫画賞など。
☆クマガイコウキ
映像作家、劇作家。1961年生。宮城県在住。
映画『ぼのぼの/クモモの木のこと』監督、脚本。児童劇団AZ9 ジュニアアクターズ座付作家。長編紙芝居『蛇蝎姫と慚愧丸』脚本、演劇『タルタロスの足湯』脚本など多数。
☆小高功太(こだか・こうた)
2000年生。神奈川県在住。
第31回伊藤園お~いお茶新俳句大賞佳作特別賞。第28回伊藤園お~いお茶新俳句大賞佳作。第2回奈良マラソン短歌コンテスト佳作。
☆齋藤 貢(さいとう・みつぐ)
詩人。1954年生。福島県在住。
詩集に『奇妙な容器』(詩学社・1987)、『夕焼け売り』(思潮社・2018)など多数。
第40回福島県文学賞、第37回現代詩人賞受賞など。
☆佐々木貴子 (ささき・たかこ)
詩人。1970年生。宮城県在住。
2012年「詩とファンタジー」大賞。第26回詩と思想詩人賞。第7回びーぐるの新人。詩集『嘘の天ぷら』(土曜日術者出版販売・2018)にて第30回歴程新鋭賞。「ココア共和国」編集。
☆能美政通(のうみ・まさみち)
詩人。1980年生。秋田県在住。第61回福島県文学賞詩部門準賞。
あきた県民芸術祭2012 詩部門入選。
第1回いがらしみきお賞受賞。
☆真土もく(まつち・もく)
詩人。2002年生。三重県在住。
第6回YS賞受賞
☆森島永年(もりしま・ながとし)
脚本家。1955年生。静岡県在住。
劇団「月虹舎」元主催、脚本担当。
山本寛斎「心エネルギー」、山海塾「卵熱」などに関わる。代表作「どぶ板を踏みぬいた天使」(脚本担当)。
☆八城裕貴(やしろ・ゆうき)
詩人。2000年生。宮城県在住。
第1回秋吉久美子賞受賞。
紙の本はこちらから
2021年 ココア共和国9月号
2021年 ココア共和国8月号
2021年 ココア共和国5月号
2021年 ココア共和国4月号
2021年 ココア共和国3月号
2021年 ココア共和国2月号
2021年 ココア共和国1月号
2020年 ココア共和国12月号
